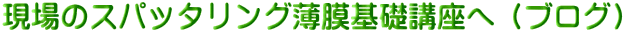|
|
|

|
|
|
小島啓安 博士(工学) 名古屋大学 客員教授
|
お問い合わせは、まずはEメールで: TEL080-8083-2403
|
スパッタリングプロセスによる薄膜事業の 研究・開発・生産 をサポートします。
長期から短期まで各種コンサルティング業務
- プラスチック,ガラス、金属基板など
- 多品種少量生産、量産装置など
- 金属膜、化合物膜、傾斜膜、多層膜など
- 装置開発、改造、コストダウン,密着性,アーキング(異常放電)などのトラブル対策まで
- お気軽にご相談ください。
薄膜技術は、複雑な要因が絡み合って、何がその解決に必要なのか判断が難しいです。多くの経験をもとに、優先事項を絞り込み、短時間にて解決する道筋を提供します。

日刊工業新聞社より「現場のスパッタリング薄膜 Q&A」第2版を出版しました。437ページ3560円税込みです。初版に比べて、プラズマ密度の測定、ロータリーカソードなどの追加、および新しく”未来へ”という項目で、今後のスパッタ膜の可能性を考えてみました。
初版の出版から14年、第2版から7年が経ち、多くの方にご購入頂き有難うございます。この本は、できるだけ具体的にスパッタ技術を理解して頂くために、グラフや図を多用して分かりやすくしております。ノウハウなども含め詳細に記述したつもりですが、それでも現場で生じる様々なトラブルや現象のすべてを網羅することは、紙面の制約上できません。コンサルでは、この本に書ききれなかったノウハウを含めて解説をしながら、多くの問題に取り組んでおります。やはり現場で難題に直面するたびにスパッタ技術の奥深さに触れますし、スパッタ技術のさらなる可能性も感じております。今後も、スパッタ技術の向上にささやかながら貢献し、多くの現場のスパッタ技術者にコンサルを通じてお手伝いが出来れば幸いです。
コンサルティング開始までのながれ
1、メールにてご連絡頂きます
ご依頼内容について概要をお知らせください
製造トラブルか、開発についてのコンサルか等の概要で結構です。
初回の打ち合わせの日程、場所等についてご希望をお伝えください。
2,秘密保持契約(NDA)を結びます
具体的な内容を伺うことになりますので、初回打ち合わせ前までにNDAを結びます
3,初回打ち合わせを行います。無料です。1時間程度
リモートなどを用いた打ち合わせを行います。対面での打ち合わせの場合には、打ち合わせ場所までの交通費実費を頂きます。(東京都区内、横浜近隣は、不要です)
素材の材質、形状、成膜プロセス、現状のトラブル内容、開発目標など
成膜プロセスに関しては、スパッタ以外にもイオンプレーティング、真空蒸着対応可能です。
ご依頼内容についての詳細確認、技術的見通しなどの協議を行ったうえで、コンサル期間や料金についての
の打ち合わせを行います。
4,コンサル開始
上記合意に至った場合には、契約書を交わしコンサル開始します。
現状のデータ、現場の装置、プロセスを確認しながら、コンサルを進めます。
その他
生産工程上の品質に係るお急ぎの場合には、別途対応いたします。
コンサルにおいては、すべてご依頼通りに解決できるかは保障できませんが、幸いにも、現在までトラブル依頼頂いた件は、およそ解決に至っています。
トラブルシューティングは、やはり多くの事例で経験を重ねて来たことが大きな力となっています。
難しいテーマ歓迎します。ご相談は、お早めに❕
オープンイノベーションが注目されています。グローバル市場での競争の激化、消費者ニーズの早い変化に対応するために、従来型の自前主義の閉鎖的方法ではなく、必要な研究開発能力、技術、を広く外部市場から調達し効率的なイノベーションを目指すいわゆるオープンイノベーションが世界の潮流となってきています。これらの動きに、貢献することが、目標です。
スパッタリングの技術紹介
金属ターゲットを用いる金属膜や反応性スパッタでは、ロータリーカソードは有効ですし、新規機能膜の作成には、HIPIMS電源は、新しい可能性があります。スマホやディスプレーには、ロールコーターが不可欠な装置となります。また、近年の開発期間の短縮、ターゲット利用率の向上などの開発補助手段として、シミュレーションの活用が現実的な手段として利用が広がっています。
技術解説:スパッタリングと密着性向上
薄膜コーティングにおける密着性は、製品化する場合に大変重要なコンテンツです。コーティングは、基板の表面に薄膜をスパッタして作成し、様々な機能を付加することで、新たな価値を創成します。そこで密着性が悪く剥がれてしまったら、コーティングの役割は果たせませんし、価値が無くなってしまいます。生産現場にて、密着性を向上する、密着性を維持した安定な生産条件を構築することは、コーティング製品の必須条件です。
密着性を向上するポイント
①基板、ターゲット及びチャンバー内の清浄化
②基板と膜の相互作用の最大化 物理的なアンカー効果、化学的な反応による結合効果
③薄膜全内部応力の最小化
これ等のポイントを考えながら、密着性を向上するスパッタプロセス条件を検討します。スパッタ条件は、多くの場合にトレイドオフの関係にあります。使用する装置のコンポーネント(電源、カソード、アノード、ガス配管、排気ポンプ、モニター、基板搬送機構など)の最適化を図りながら、スパッタ条件を決定します。また、アーキング(異常放電)には、注意が必要です。ターゲットなどに、痕跡がないかチェックしたら良いかと思います。
密着性に関しては、「密着性のあれこれ」と題して、解説しました。興味のある方は、チェックしてみて下さい。
コンサル業務の実績について
・当社へお問い合わせ頂いたメーカーの方からコンサル実績についてのお問い合わせが時々あります。
・コンサル業務は、信頼関係が重要ですので、個別の内容を開示するのはできませんが、概要のみお伝えできればと思います。
・現在まで、海外を含めますとおよそ30社以上の大企業及び中堅メーカーのコンサルティングを行って参りました。
・業種も内容も多岐にわたっています。
・開業から19年たちました。だんだん難しいテーマも増えてきましたが、何とか解決策を見つけて、満足して頂いているという
のが、仕事の支えとなっています。
・内容的には、やはり日常業務で生じる、密着性にかかわる膜剥がれ、クラック、ボイドや フィルム基板でのしわ対策などが
多いです。その他に、装置の入れ替えによる条件だし、長時間成膜中での膜質変化対策などもあります。
・開発案件でもこのような密着性に係るものが多いですが、プロセス条件の最適化やターゲット材料に係る問題、最適プロセス
のテーマもあります。最適プロセスの中には、驚くような用途の場合もあります。
・開発案件ですと、特許の問題がありますが、特許については、こちらからアドバイスしたアイデアでもすべて依頼主
側の所有となります。
・コンサル期間ですが、製造工程上のスパッタトラブルの解決のような場合には、1回のお打ち合わせで解決終了した場合も
ありますし、膜分析や装置の改造、新設などを伴う場合には、相応の期間がかかりますので、2~3年になる場合もありま
す。社内スパッタの勉強会(講習会)の依頼もありますし、社内プレゼンの資料作りのお手伝いもあります。
・スパッタに関する技術顧問的な役割の契約もありますので、その場合には、長期の契約も可能です。
・コンサルを依頼いただいた場合には、内容をお伺いした日から、守秘協定を結びますのでご安心頂ければと思います。
・基本的には、装置を見ながら現場にてのお打ち合わせを行っております。この2年ほどは、新型コロナの影響でリモート
打ち合わせをしていましたが、この6月より対面打ち合わせを再開いたしました。
・スパッタに限らず蒸着、薄膜などドライプロセスに係る技術でお困りの技術者のお手伝いが出来ればと心がけておりますの
で、お気軽にご連絡ください。まずは、メールにて相談頂ければと思います。以下にアドレスとなります。
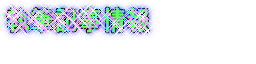
- 日刊工業新聞社:2008年8月「現場のスパッタリング薄膜Q&A」の本を出版。384ページ 3150円(税込) 小島啓安著
- 真空ジャーナル:2008年1月号(Vol116)に、特集記事「高速スパッタリング」の解説
- (株)情報機構:2007年8月「ディスプレー光学部材における薄膜製造技術」に、「スパッタリングにおけるトラブル対策」執筆
- (株)技術情報協会:2007年7月「ぬれと(超)撥水、(超)親水技術、そのコントロール」に、「大気圧プラズマ親水化処理によるFPD基板洗浄技術への応用」執筆
- コンバーテック 2008年10月号「現場に見るスパッタ法による薄膜化技術と応用」 など執筆掲載
- (株)技術情報協会2009年1月「スパッタ実務Q&A集」 反応性スパッタ、ターゲットなどに関するQ&A執筆
- 加工技術研究会 2009年10月 「新コーティングのすべて」に 「現場に見るスパッタ法による薄膜化技術と応用」執筆
- シーエムシー出版 2011年3月「ロールtoロール技術の最新動向」に「ロールtoロールスパッタプロセスにおける成膜速度の向上」執筆
- シーエムシー出版 2011年4月 「最新ガスバリア薄膜技術」に「反応性高速スパッタ技術」執筆
- サイエンス&テクノロジー 2012年8月「フィルム加工トラブル対策技術」に「スパッタリングにおける成膜過程の問題」執筆
- (株)技術情報協会2013年4月「フィルム成型・加工とトラブル対策」に「ロールtoロールプロセスにおける成膜速度向上と膜欠陥への対策」執筆
- (株)技術情報協会2013年6月「光学薄膜の最適設計・成膜技術と膜厚・膜質・光学特性の制御」に「反応性高速スパッタ法による光学薄膜の作製技術と膜質制御」執筆
- 表面技術協会2013年7月特集「最近のスパッタリング動向」に「低ダメージのためのロータリーカソード技術と高速成膜技術」を執筆
- 日刊工業新聞社:2015年2月「現場のスパッタリング薄膜Q&A」第2版を出版。437ページ 3560円(税込)
- 表面技術協会2016年12月特集「車載用カメラの反射防止膜技術」を執筆
- 表面技術協会2017年12月特集「最新のPVD技術」執筆
スパッタ技術を支えている技術者の方々へ
スパッタの技術者は、どの企業でも少ない人数の場合が多く、開発や生産上のトラブルが生じても個別に悩み、なかなか周りからの支援が得にくい環境にあります。これは、私の過去の経験でもあります。生産条件などを変える場合には、さらに勇気が必要です。まさか「・・・・の要因」がトラブルの原因だとは思わなかった。。。というお客様の声を多く頂きます。トラブルの解決が遅れれば損失が生じますし、商品の信頼性も損ないます。また開発が遅れれば特許の取得で不利になりますし、先行利益を得られないなどの状況が生じます。これらの問題の解決に貢献ができること。これが私たちの大きな喜びとなっています。私たちは、スパッタリングだけでなく、真空蒸着など両方のプロセス開発と生産現場の支援に深くかかわり続けてきました。そのためプロセスの最適な選択についても、長い経験が大きな強みとなっています。第3者の支援、アドバイスは、心強いものがあるかと思います。そういう期待に応えられればと思い、日々精進しております。スパッタに関する何でも相談室を目指しています。
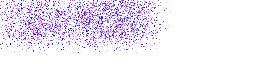
******* 河津バガテル公園の秋バラです。*******
河津町は、伊豆の中でも南に位置していて温暖な気候です。冬の2月に咲く河津桜
が有名ですが、バガテル公園の春、秋バラも美しいです。癒されますね。
ちょっと一服してください
今回のテーマ は「薄膜の内部応力」です。
前回は、スパッタに関する技術用語の1回目として「アーキング(異常放電)」を取り上げました。今回は、2回目として「薄膜の内部応力」についてです。基本的には、「現場のスパッタリング薄膜Q&A 第2版」 をベースにしております。
一般的には、内部応力を下げることにより、膜剥がれなどの対策を行いますが、ハードコートのような硬さが必要な膜の場合には、内部応力を増加して対応する場合もあります。 興味がある方は、ブログにお立ち寄りください。